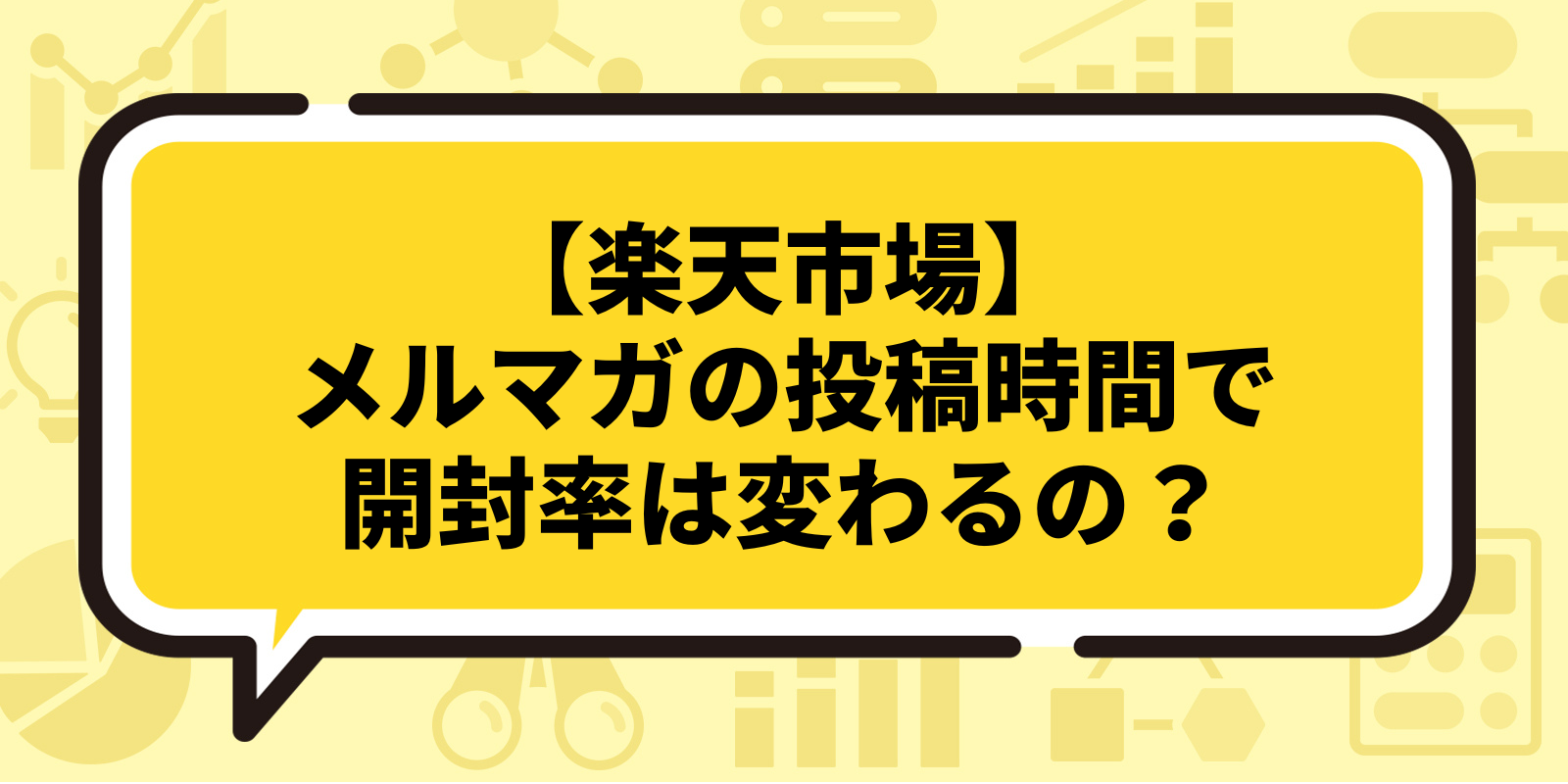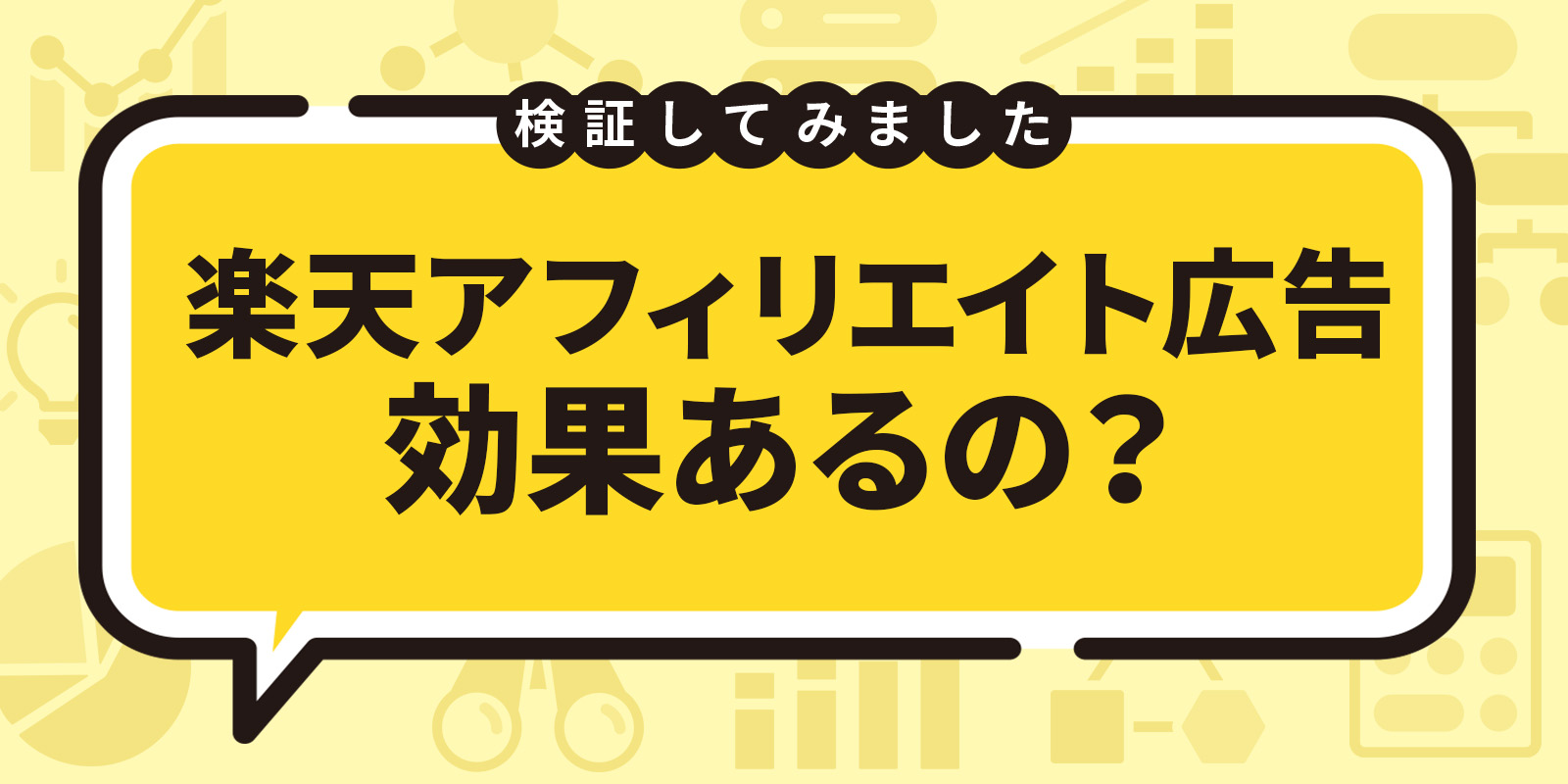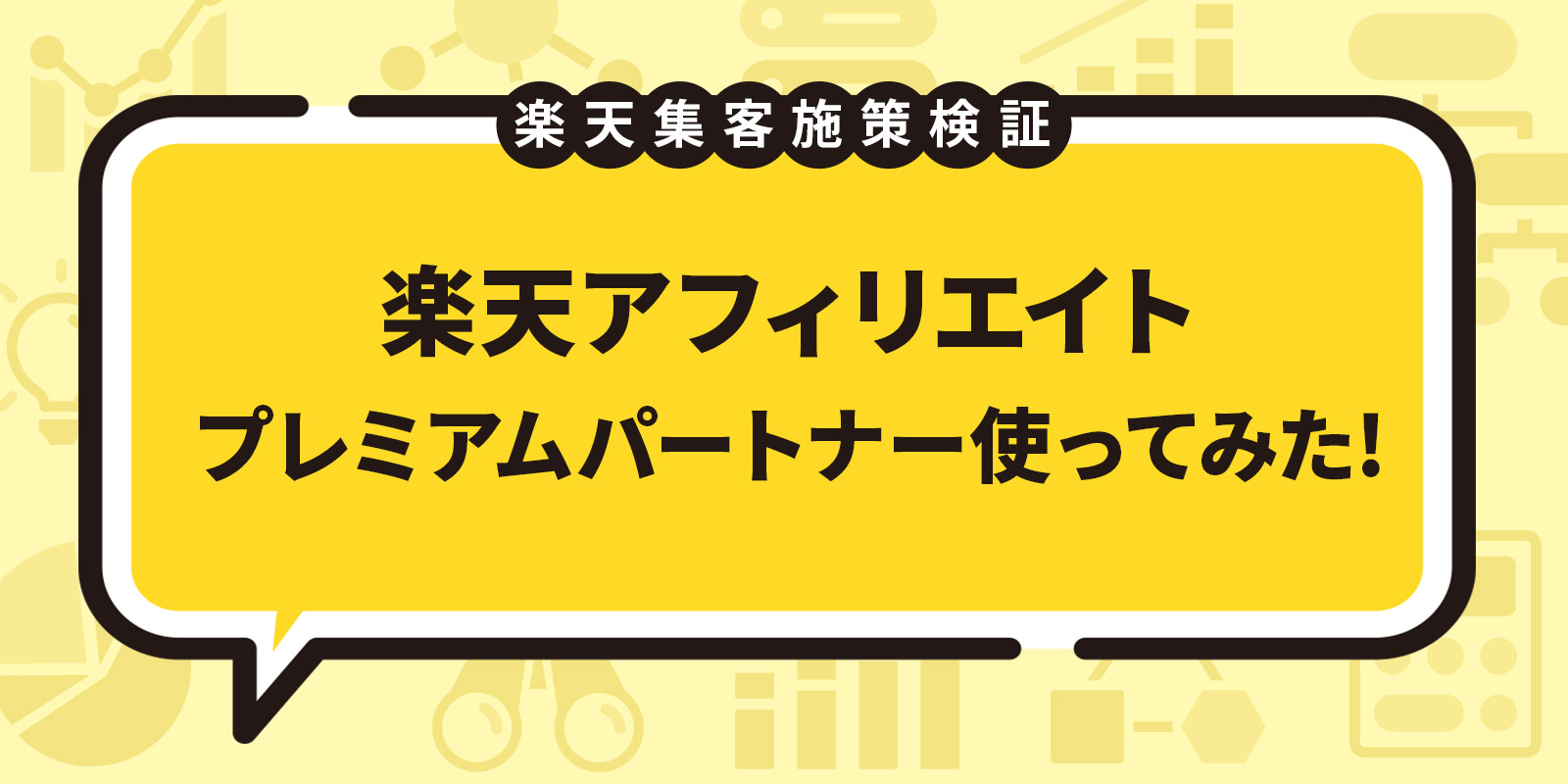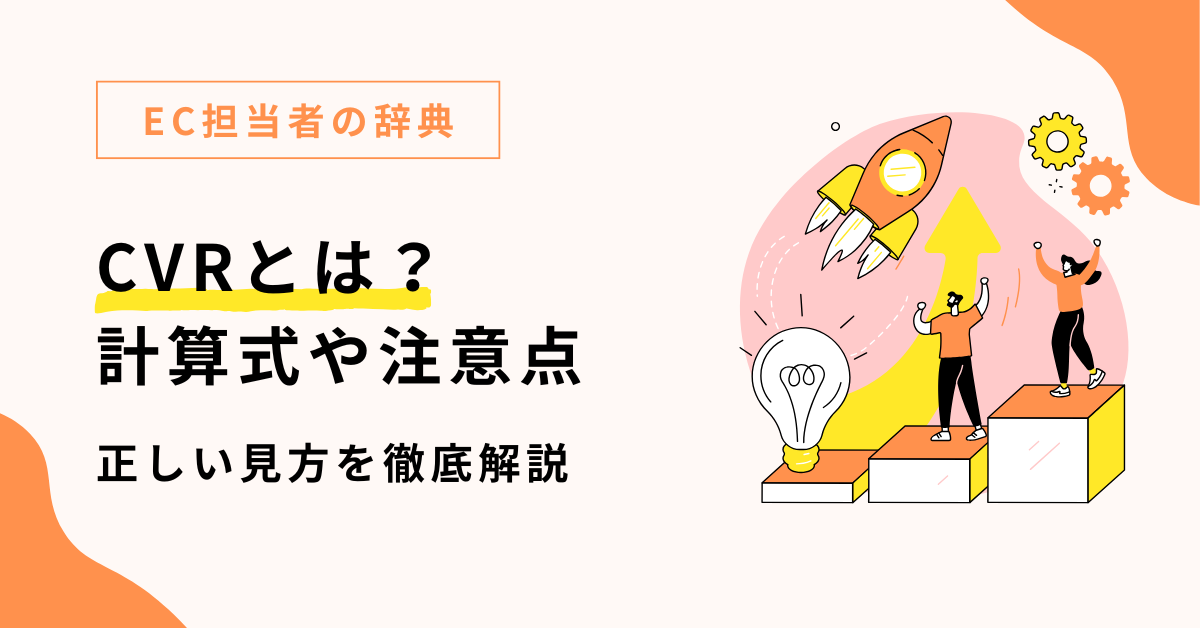テーマ:化粧品の広告はどこまでOK?薬機法で定められた範囲を解説!
化粧品では、効果として言っていいことが“56項目”に決められているのを知っていますか?たとえば「肌をなめらかにする」「毛髪にツヤを与える」など、化粧品がうたえる効能効果は薬機法で細かく定められているんです。
この記事では、マーケティング分野で10年以上の経験を持つ広告運用のプロフェッショナル先輩社員Aさんと、薬機法や景表法は初心者の新人社員Bさんが基礎知識を一緒に学んでいく様子をお届けします。難しい法律もありますが、AさんとBさんの会話を通じて一緒に理解を深めていきましょう!

薬機法と化粧品

新人社員Bさん:先輩、この前「薬機法で決められてる化粧品の効果って限られてる」って聞いたんですけど、実際どのくらい決まってるんですか?
先輩社員Aさん:かなり細かく決まっているんですよ。たとえば「肌のキメを整える」「肌にツヤを与える」「毛髪にハリ・コシを与える」などですね。
新人社員Bさん:そんなに明確に決まっているんですね。では、それ以外の表現を使うと違反になってしまうんですか?
先輩社員Aさん:その通りです。化粧品は「清潔にする、美化する、魅力を増す」といった目的に限定されています。今日は、化粧品で認められている効能効果を一緒に見ていきましょうか。
新人社員Bさん:お願いします!
この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年八月十日)(法律第百四十五号)
化粧品の効能の範囲とは

先輩社員Aさん:実は、化粧品で言っていい効果の範囲は全部で56項目に整理されているんです。つまり「この56項目の中に含まれる内容だけ」が化粧品として表現できる範囲ということですね。たとえば「肌をなめらかにする」「毛髪をしなやかにする」「肌を引きしめる」などです。どれもおだやかに整えることを目的とした表現ですね。「ターンオーバーを促す」や「代謝を高める」といった体の機能そのものを変える表現はNGなんです。
新人社員Bさん:同じように聞こえても整えると変えるでは意味が違うんですね。
先輩社員Aさん:そうなんです。そこを間違えると薬機法違反になってしまうこともあります。だからこそ、この56項目の範囲を正しく理解しておくことが広告づくりの基本になるんですよ。以下は化粧品の56の効能効果です。
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひげそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。
注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
出典:化粧品の効能の範囲の改正について(平成23年7月21日)(薬食発0721第1号)各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知より
化粧品での違反事例

新人社員Bさん:なるほど!ただ、実際の広告ってつい効果を強く言いたくなることも多いと思うんです。どんなケースが違反になるんですか?
先輩社員Aさん:よくあるのは「改善」や「修復」といった言葉を使ってしまうパターンですね。化粧品はおだやかに整える範囲でしか効果を訴求できません。代表的な違反例をカテゴリごとに見てみましょう。
スキンケア編
「肌のバリア機能を修復する」
「シミを薄くする」
「シミを消す」
「肌のターンオーバーを整える」
「ハリを回復させる」
「若々しい肌に導く」
「シワを目立たなくする」
「たるみを引き上げる」
「毛穴レスの肌へ」
「肌トラブルを根本から改善する」
「コラーゲンの生成を促す」
ヘアケア編
「傷んだ髪を修復する」
「ダメージを補修してよみがえらせる」
「根本からハリを出す」
「頭皮環境を改善する」
「髪の成長を促す」
「失われたツヤを取り戻す」
口腔ケア編
「ホワイトニング効果で黄ばみを落とす」
「歯の黄ばみを改善する」
「歯石を除去する」
「歯茎の血行を促進する」
「口臭を根本から消す」
「原因菌を殺菌する」
先輩社員Aさん:これらの表現に共通しているのは体や肌の働きそのものを変えるように聞こえる点です。「改善」「修復」「回復」「促進」「取り戻す」といった言葉は、人体への作用を連想させるため化粧品では使えません。化粧品に求められているのは、変化を謳うことではなく日々のケアを通じて心地よさや美しさをサポートするというスタンスなんです。効果を強く伝えたい気持ちがつい法律のラインを越えてしまうケースが多いんです。
化粧品での言い換えテクニック

新人社員Bさん:気をつけるべき言葉はわかってきました。ただ、広告って商品の良さを伝えたいのでつい効きそうな表現を使いたくなります。違反にならないようにするにはどう言い換えればいいでしょうか?
先輩社員Aさん:ポイントは変化を断定する言葉を避けて、整える・保つ・守る・印象といったおだやかな表現に言い換えることです。例えば、こんなふうに置き換えると自然で安全ですよ。
| NG例 | OK例 |
| 「肌のバリア機能を修復する」 | 「肌をすこやかに保つ」「乾燥から肌を守る」 |
| 「シミを薄くする」 | 「明るい印象の肌へ」 |
| 「たるみを引き上げる」 | 「ハリ感のある印象に導く」 |
| 「傷んだ髪を修復する」 | 「毛先までなめらかに整える」 |
| 「口臭を根本から消す」 | 「口内をすっきりと保つ」 |
新人社員Bさん:言い換えるだけで印象がやわらかくなるし、上品な感じにもなりますね。
先輩社員Aさん:そうなんです。化粧品の広告は前向きに整えていくイメージを持たせることで、薬機法にも景表法にも触れずに商品の魅力をしっかり伝えられますよ。
Q&A この表現言える?言えない?

ここからは当社でもよくご質問いただく表現について先輩社員Aさんが解説します。
Q. 「乾燥による小ジワを目立たなくする」という表現は化粧品で認められていますか?
A. 条件を満たせば使用可能です。厚生労働省が定める「56の効能効果」のうち(56)に該当する項目ですが、日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づいた試験を実施し、その効果を科学的に確認できている場合に限り使用が認められています。つまり、根拠となるデータがない状態で使用すると薬機法違反にあたる可能性があります。また「小ジワを目立たなくする」だけではNGで、必ず「乾燥による」という原因を明示する必要があります。
Q. 「シミを薄くする」「シミを消す」という表現は化粧品で使用可能ですか?
A. 使用できません。「明るい印象に導く」といった印象表現に留める必要があります。医薬部外品で有効成分が配合されている場合は「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」という表現が認められています。ただし、あくまで「防ぐ」までであり「消す」「薄くする」といった効果の断定はできません。
Q. 「肌のターンオーバーを整える」という表現は薬機法上問題ありませんか?
A. 問題があります。「ターンオーバー」は皮膚の代謝機能を指すため、体の働きを変えるような印象を与えてしまいます。そのため化粧品では使用できません。「キメを整える」「うるおいを与えてなめらかにする」など、肌表面の状態をおだやかに整える表現に言い換えるのが適切です。
まとめ

・化粧品で認められる効能は「56の効能効果」の範囲内のみで、それ以外の効能効果は基本的に認められていない
・「改善」「修復」「促進」「根本から」などの表現はNG
・効果を断定・誇張する表現は避け、整える・保つ・守る・印象で伝える
先輩社員Aさん:広告表現においては、法令遵守と同時に消費者に信頼感を与えることが重要です。事実に基づいた効果を正確に伝え、化粧品の効果を最大限に引き出しましょう。
新人社員Bさん:わかりました。正確で誇張のない表示を心掛けることが大切なんですね。
先輩社員Aさん:その通り。消費者に対して正直で透明性のある情報を提供することが、企業の信頼を築くためにも重要です。法律を遵守することで、長期的には企業のブランド価値を高めることができます!
新人社員Bさん:ありがとうございました!薬機法・景表法についての理解が深まりました。これからは広告や製品表示に一層注意を払っていきたいと思います。
先輩社員Aさん:どういたしまして。何か不明点があればいつでも聞いてくださいね!
・・・
最後までお読みいただきありがとうございます。
広告表現は表示の受け手である「一般消費者」にどう捉えられるかが争点となりますので、以前はOKだった表現が時代の流れと共にNGとなることもあります。また、見る人が変わればOKだと思われる表現もNGになる可能性も。誰が見ても正しく伝わる表現を意識し、常にアンテナをはって正しい知識を持つことや、プロの見解も交えながら訴求することで、お客様が安心してお買い物できる環境となり、企業も守ることになります。
皆で正しい広告表現を目指していきましょう!
マクロジでは、制作物の全てを広告審査しております。サービスについては以下からお問合せください。
関連リンク
化粧品・医薬部外品で「美白」「ホワイトニング」は表現できる?言い換え含め薬機法・景表法に基づき徹底解説
化粧品/医薬部外品/美容機器で「保湿」「うるおい」は表現できる?言い換え含め薬機法・景表法に基づき徹底解説
化粧品/医薬部外品で「エイジングケア」「アンチエイジング」は表現できる?言い換え含め薬機法・景表法に基づき徹底解説
化粧品で「ピーリング」「ターンオーバー」は表現できる?言い換え含め薬機法・景表法に基づき徹底解説
株式会社マクロジと広告表現チェックツール『コノハ』を運営する(株)アートワークスコンサルティング、広告チェック領域で業務提携